備品・消耗品管理をラクにする最新ノウハウ2025年版
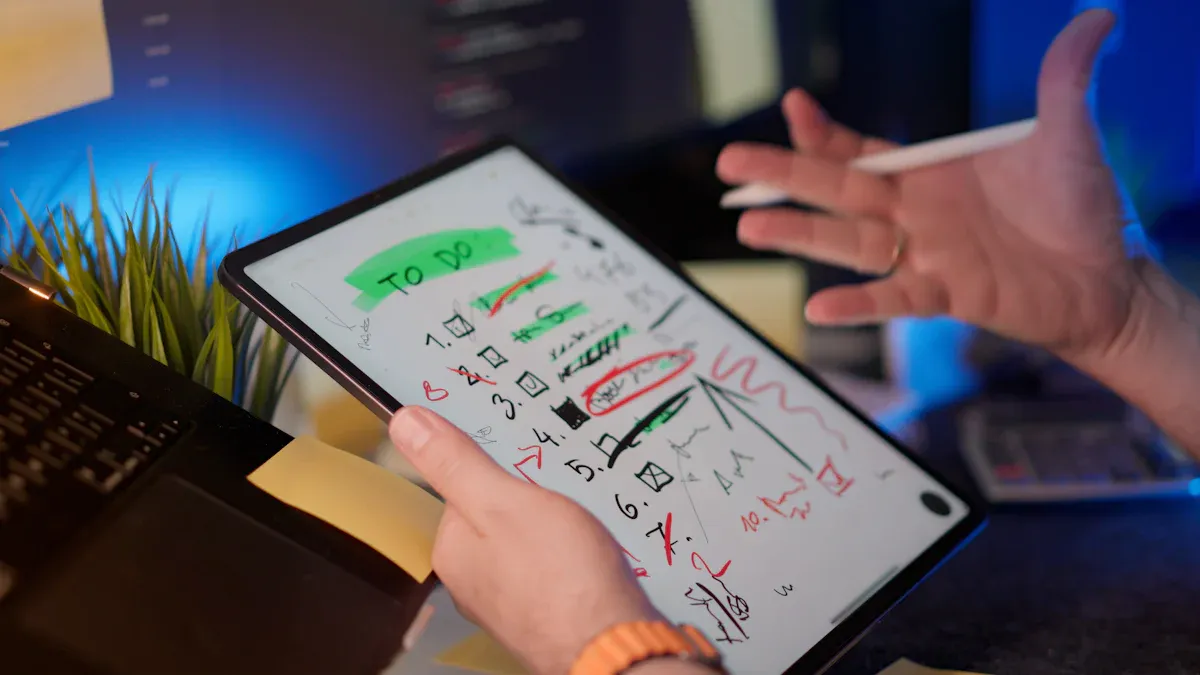
企業は日々、備品や消耗品の管理に多くの時間とコストを費やしている。近年、AIやIoTの進化により、物品管理効率化の方法が大きく変わってきた。たとえば、クラウドベースのシステムや自動化技術の導入で、リアルタイムな在庫把握やコスト削減が実現している。
物品管理システムはユーザー数に応じたプラン選択が重要
必要な機能だけを選べばコストを抑えられる
AIとIoTによる自動化で業務効率とコスト削減が進む
クラウド化でリアルタイム管理が可能
下記のように、AIやデジタル技術の導入で劇的な業務改善が報告されている。
事例 | 効果 |
|---|---|
ワークマン | 発注業務時間を30分から2分に短縮 |
北米の大手製造メーカー | 在庫コストを約3割〜5割削減 |
薬局 | 在庫管理業務を2時間から1時間に短縮 |
誰でもすぐに実践できる方法が存在する。Cloudpickのような最新ソリューションを活用すれば、業務の効率化とコスト削減を同時に実現できるはずだ。
重要ポイント
物品管理システムは、必要な機能を選ぶことでコストを抑えられる。無駄な支出を防ぎ、効率的な運用が可能になる。
AIやIoTを活用した自動化により、業務効率が向上し、コスト削減が実現する。これにより、時間を有効に使えるようになる。
クラウドベースの管理システムを導入すれば、リアルタイムで在庫状況を把握できる。これにより、業務の中断を防ぎ、スムーズな運営が可能になる。
物品のラベリングと管理ルールの策定は、現場の混乱を防ぐ重要なステップである。明確なルールを設けることで、ミスを減らせる。
小さな改善から始めることで、現場の納得感を得やすくなる。成功体験を積み重ねることで、全社的な効率化が進む。
物品管理効率化の全体像

効率化の基本
物品管理効率化は、企業の業務負担を軽減し、コスト削減やミス防止につながる重要な取り組みである。現場では、備品の整理ルール作成や台帳の整備、ラベリング、保管場所の選定、定期的な棚卸しなどが基本手法として採用されている。PDCAサイクルの活用や専用アプリの導入も一般的だ。
効率化のフレームワークとしては、BPMNによる業務プロセスの可視化や、トヨタ生産方式の「7つのムダ」などが注目されている。これらは業務の属人化や非効率を防ぎ、全体像の共有を促進する。
フレームワーク名 | 説明 |
|---|---|
BPMN | 業務の流れを図で整理する国際的な記法。業務プロセスの可視化により、業務の属人化やミスを防ぎ、全体像を共有しやすくする。 |
7つのムダ | トヨタ生産方式で知られるフレームワークで、業務内の非効率を発見し改善するための手法。具体的には、加工のムダ、手待ちのムダ、運搬のムダなどが含まれる。 |
物品管理効率化によるメリットは多岐にわたる。棚卸や検品作業の効率向上、記載ミスの削減、コスト削減、返却漏れ防止、属人化の防止などが挙げられる。
最新トレンド
近年、物品管理効率化の分野ではAIやIoT、クラウド技術の活用が主流となっている。AIは需要予測や在庫計画の精度向上、ピッキング効率の改善、エネルギー消費の管理などに貢献している。クラウドベースの管理システムは、リアルタイムで物品情報にアクセスでき、継続的な改善を支援する。
AIとIoTの活用による自動化
クラウドベースの管理システム
サステナビリティ対応の強化
モバイルデバイス対応の進化
市場規模も拡大傾向にあり、2024年には1兆8,420億円に達している。製造業やサービス業では、デジタル化やデータ解析の進展が物品管理効率化をさらに加速させている。
備品・消耗品管理の基礎
備品と消耗品の違い
企業や学校では、備品と消耗品を正しく区別して管理することが重要である。備品は長期間使用できる物品を指し、消耗品は使うことで減っていくものや、短期間で使い切るものを指す。下記の表は、備品と消耗品の違いをわかりやすくまとめている。
項目 | 定義 | 特徴 |
|---|---|---|
消耗品費 | 文房具などの消耗品の購入費や、購入価格が10万円未満または使用可能期間が1年未満の什器備品の購入費 | 使用によってなくなる(消耗・消費する)ものに関連する支出を示す勘定科目。 |
雑費 | 消耗品費と似た勘定科目で、消耗品とは異なる支出を示す。 | 消耗品費とは異なり、使用によってなくならない支出を含む場合がある。 |
備品はパソコンや机、椅子など長く使うものが多い。一方、消耗品はコピー用紙やペン、クリップなど、日々消費されるものが該当する。管理方法や会計処理も異なるため、区別して台帳に記録する必要がある。
管理のメリット
備品や消耗品を適切に管理することで、さまざまなメリットが生まれる。物品管理効率化を目指す企業や組織では、次のような効果が期待できる。
貸出や返却の履歴を管理することで、誰がどの備品を使っているかが明確になり、紛失や私物化のリスクが減少する。
よく使われる備品や消耗品の使用状況を把握できるため、無駄な購入を防ぎ、コスト削減につながる。
備品が破損や紛失した場合、どの段階で問題が発生したかを特定でき、責任の所在が明確になる。
定期的な棚卸しや履歴管理により、データの不一致や誤差を早期に発見できる。
修理履歴を記録することで、備品の寿命を延ばし、適切なタイミングでのメンテナンスが可能になる。
リアルタイムで在庫数を把握できると、業務の中断を防ぎ、効率的な運用が実現する。
誰がいつどれだけ消耗品を持ち出したかを記録することで、不正利用や盗難リスクを軽減できる。
適切な管理を行うことで、無駄の排除やコスト削減だけでなく、業務全体の透明性と信頼性も向上する。
管理効率化のステップ
台帳と分類
物品管理効率化を実現するためには、まず台帳の整備と物品の分類が不可欠である。企業や組織は、物品ごとに管理台帳を作成し、種類や用途ごとに分類することで、在庫状況を正確に把握できるようになる。
台帳には品名、数量、保管場所、担当者、購入日などの情報を記載する。
物品を「備品」「消耗品」などのカテゴリに分けて管理する。
定期的な更新と見直しを行い、情報の正確性を保つ。
実際に、在庫管理システムの導入によって棚卸期間が2日から1日に短縮された事例がある。RFID技術を活用した棚卸では、作業時間が10分の1に削減された。ハンディターミナルを使うことで、高い場所にある在庫の棚卸作業も容易になった。これらの工夫が、物品管理効率化の基盤となる。
ラベリングとルール化
物品のラベリングと管理ルールの策定は、現場の混乱やミスを防ぐ重要なステップである。
すべての物品にラベルを貼付し、識別しやすくする。
ラベルには品名、管理番号、使用期限などを記載する。
持ち出しや返却のルールを明確にし、従業員全員に周知する。
物流業界では、自動ラベリングシステムの導入によって誤出荷率がほぼゼロに低下し、処理件数が30%以上増加した。食品業界では自動生成機能付きラベルプリンタの導入でエラー率がほぼゼロとなり、作業時間も大幅に短縮された。小売業ではモバイルラベルプリンタの活用で作業時間が半分以下になり、医療分野では一体型ラベリングシステムによりトレーサビリティが確保されている。
適切なラベリングとルール化は、現場の混乱を防ぎ、物品管理効率化を大きく後押しする。
棚卸しの自動化
棚卸し作業の自動化は、業務負担の軽減と正確性向上に直結する。
自動化ツールやシステムを導入し、棚卸し作業を効率化する。
棚卸しの進捗や結果をリアルタイムで記録する。
棚卸しが困難な工程については、作業方法の見直しや改善活動を行う。
自動化によって人件費や保管コストを削減できる。増員せずに作業を進められるため、日常業務への影響も最小限に抑えられる。在庫の適正量を把握することで、過剰在庫や在庫ロスを大幅に減少できる。倉庫スペースの有効活用や保管費用の削減にもつながる。
棚卸し作業が長引くと日常業務に支障をきたすため、効率化と正確性の両立が重要である。
クラウド・スマホ活用
近年では、クラウドサービスやスマホアプリを活用した物品管理が主流となっている。
クラウド型在庫管理システムを導入し、どこからでも在庫状況を確認できるようにする。
スマホアプリを使って、現場でリアルタイムに在庫を登録・確認する。
デジタル管理により、手書き帳簿のミスや手間を削減する。
株式会社ウチダレックはzaicoの導入で在庫数を4割削減し、過剰在庫の問題を解決した。二村医院では在庫管理を主導できるようになり、コストや無駄の改善を実現した。コムネット株式会社は発注点管理機能を活用し、適正在庫での運用に成功している。スマホアプリの活用でリアルタイムの在庫管理が可能となり、適切な在庫量を把握できるようになった。手書き帳簿からデジタル管理への移行で、ミスを減らし効率的な物品管理効率化が実現している。
また、約6割の企業が何らかのクラウドサービスを利用しているという調査結果もある。
クラウドやスマホの活用は、今後の物品管理効率化のスタンダードとなる。
CloudpickのAI無人店舗

物品管理効率化の実現
Cloudpickは、AI技術を活用した無人店舗やスマート倉庫ソリューションを提供するブランドである。AI無人店舗は、物品管理効率化を実現するための革新的な手段として注目されている。CloudpickのAI無人店舗は、AIカメラや重量センサーを用いて、商品のピッキングや在庫状況を自動で記録する。これにより、従来の手作業による在庫管理や棚卸しの手間を大幅に削減できる。
AI無人店舗の導入によって、さまざまな業界で業務効率が向上している。たとえば、ファミリーマートではAIとIoTを活用し、来店者データを基に商品発注や店舗レイアウトを最適化している。イトーヨーカ堂は132店舗でAI発注システムを導入し、販売数の最適化を実現した。ライフではAIによる需要予測システムを活用し、発注時間を5割以上削減した。杏林堂薬局では、AI導入により月25時間のデータ処理時間を短縮した。京東のAIスマート倉庫では、従来の10倍の生産性を達成している。
CloudpickのAI無人店舗は、24時間365日営業が可能であり、レジ待ちのストレスを解消する。人手不足や人件費の高騰といった社会課題にも対応できる。AIによるリアルタイムな在庫管理や自動発注機能は、過剰在庫や欠品リスクを減らし、効率的な運営を支える。
AI無人店舗の普及により、物品管理効率化が加速し、企業の競争力向上に寄与している。
AI無人店舗の特徴
CloudpickのAI無人店舗は、最新のAI技術と多次元センサーを組み合わせた次世代型店舗である。主な特徴は以下の通りである。
レジ店員が不要なため、人件費を大幅に削減できる。人材不足の課題にも柔軟に対応できる。
24時間365日営業が可能で、さまざまな客層にサービスを提供できる。
精算は出口ゲートで自動的に行われるため、現金やカードの受け渡しが不要である。
顧客の店舗内での行動データを分析し、商品陳列やプロモーションに活用できる。
スマートAIカメラによる骨格追跡やプライバシー保護機能を搭載している。
棚情報のリアルタイム監視やスマート補充機能により、常に最適な在庫状態を維持できる。
モバイルやデスクトップから遠隔操作が可能で、運営コストを抑えられる。
60種類以上の決済方法に対応し、グローバル展開も容易である。
AI無人店舗市場は急速に拡大している。2022年の市場規模は606億円で、成長率は13.4%に達した。2028年には年平均成長率34.3%で、2,805億1,000万米ドルに達する見込みである。
年度 | 市場規模 (円) | 成長率 |
|---|---|---|
2022 | 606億 | 13.4% |
年 | 市場成長率 (CAGR) | 予測市場規模 (米ドル) |
|---|---|---|
2028 | 34.3% | 2,805億1,000万 |
コロナ禍の影響で、冷凍餃子の無人販売店は3年間で10倍に増加した。AI無人店舗の導入は、今後もさまざまな業界で拡大が予想される。
CloudpickのAI無人店舗は、リアルタイムな在庫管理、効率的な物品管理、そして顧客体験の向上を同時に実現する。企業はこのソリューションを活用することで、業務の自動化と省力化を推進し、持続的な成長を目指せる。
導入事例
空港での活用(上海浦東空港)
上海浦東空港では、CloudpickのAI無人店舗が導入されている。空港は世界中から多くの旅行者が集まる場所である。従来の店舗では、混雑やレジ待ちが大きな課題となっていた。Cloudpickの無人店舗は、AIカメラとIoT技術を活用し、来店者がQRコードや顔認証で入店できる仕組みを提供する。顧客が商品を手に取ると、AIが自動でバーチャルカートに追加する。レジでの精算は不要となり、スムーズな買い物体験が実現した。空港側は、運営コストの削減と売上の拡大を同時に達成している。夜間や早朝でも店舗を開けることで、利用者の利便性も向上した。
日本の事例(CATCH & GO)
日本では、NTTデータ本社にCATCH & GOという無人店舗が設置されている。この店舗はCloudpickのAI技術を活用している。スタッフの業務負担が大幅に軽減された。レジ業務が不要となり、商品補充スタッフ1人で運営できる。AIカメラと重量センサーが来店客の動きをリアルタイムで把握し、運営の効率化を実現した。購入商品の認証精度は99.8%と非常に高い。誤認識が発生した場合も、迅速な対応が可能である。
効率化効果 | 詳細 |
|---|---|
スタッフの業務負担軽減 | CATCH & GOによりレジ業務が不要となり、商品補充スタッフ1人で運営可能。 |
来店客の動きの把握 | AIカメラと重量センサーを活用し、リアルタイムで運営の効率化を実現。 |
高い認証精度 | 購入商品の認証精度は99%以上。誤認識時の対応も整備。 |
このように、CATCH & GOは日本のオフィスビルにおける新しい物品管理のモデルとなっている。
海外の事例(ドイツLidl)
ドイツの大手小売チェーンLidlは、大学キャンパス内にCloudpickのshop.boxを導入した。shop.boxは、AIとコンピュータビジョン技術を活用し、学生や教職員がアプリで登録し、QRコードで入店できる。顧客が商品を選ぶと、システムが自動で購入を記録し、会計も自動で完了する。これにより、従来のレジ待ちがなくなり、買い物のストレスが大幅に減少した。Lidlは、shop.boxの導入で運営の生産性を向上させ、データ分析による商品配置やプロモーションの最適化も実現している。学生たちは、未来型の買い物体験を日常的に楽しんでいる。
実践アドバイス
小さく始める
備品・消耗品管理の効率化は、いきなり全社導入を目指すよりも、小規模な取り組みから始めると成功しやすい。多くの企業が、まず現場単位や部署単位で試行し、成果を確認してから全体展開へと進めている。
中小製造業のA社は、定期的な棚卸しと使用率分析を実施し、未使用の消耗品を特定してコスト削減に成功した。
小売業のB社は、棚卸しデータをグラフ化し、過剰発注を防いで在庫金額を減少させた。
サービス業のC社は、季節ごとの消耗品使用パターンを分析し、需要予測を改善してコストを抑えた。
効率化のステップは明確である。
現状把握と備品台帳の作成
定期的な棚卸しと分析の実施
従業員への周知徹底
協力体制の構築
ルール策定と見直し
小さな成功体験を積み重ねることで、現場の納得感と協力が得やすくなる。
社内浸透のコツ
効率化の仕組みを社内に根付かせるには、具体的な成果を見える化し、全員がメリットを実感できる環境を作ることが重要である。たとえば、発注や支払業務の時間削減、コピー用紙の削減など、数値で効果を示すと説得力が増す。
効果の内容 | 削減時間・削減量 |
|---|---|
発注時の価格交渉時間 | 年間約525時間 |
全事務所の支払業務 | 年間約500時間 |
コピー用紙の削減 | 年間約6万枚 |
購買業務の発注時間 | 年間約171時間 |
一方で、管理ルールが曖昧だったり、エクセルや紙での管理に頼りすぎたりすると、属人化や在庫数の把握ミス、紛失・不正使用などのリスクが高まる。利用履歴が残らない場合、業務全体の効率も低下しやすい。
明確なルールと定期的な見直し、デジタルツールの活用が、社内浸透と持続的な効率化の鍵となる。
物品管理効率化の第一歩は、現場でできる小さな改善から始まる。CloudpickやAI無人店舗の導入により、データ分析や在庫管理の自動化が進み、顧客ごとに最適な提案も可能になる。今後はRFIDやWMS、ピッキングロボットなどの技術も注目される。
在庫管理システムの導入
棚卸業務の効率化
保管レイアウトの最適化
これらのアクションを実践し、継続的な改善と最新情報のキャッチアップを心がけたい。
