荷主が知っておきたい物流効率化法対応の基本手順

物流効率化法に直面し、多くの荷主企業が「まず何をすべきか」と悩んでいる。実際、次のような課題を感じている企業が多い。
課題内容 | 割合 |
|---|---|
費用対効果を得にくい | 26.0% |
取引先から理解が得られない | 13.0% |
ノウハウを持った人材がいない | 11.0% |
まず取り組むべきアクションは次の通りである。
積載効率の向上
荷待ち時間の短縮
荷役等時間の短縮
社内体制整備や関係事業者との連携
自社が対象かどうかを確認し、現状把握から始めることが重要である。小さな一歩から着実に進めることが、実践的な対応への近道となる。
重要ポイント
物流効率化法に対応するため、まず自社の現状を把握し、課題を明確にすることが重要です。
荷主は積載効率の向上や荷待ち時間の短縮に努め、物流事業者との連携を強化する必要があります。
デジタル技術を活用することで、業務の効率化やコスト削減が実現できます。AI無人店舗などの導入を検討しましょう。
PDCAサイクルを活用し、継続的な改善を行うことで、法令遵守と競争力の強化が可能です。
小さな一歩から始め、段階的に改善を進めることで、持続的な物流効率化を目指しましょう。
物流効率化法の概要
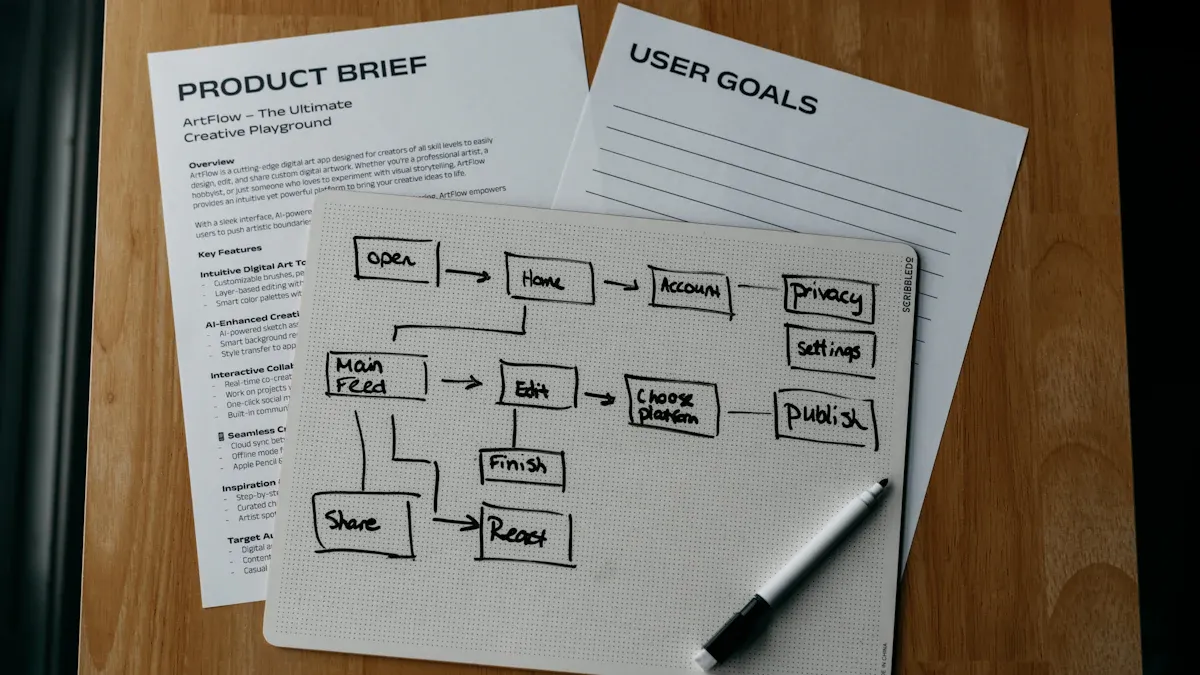
法律の目的と背景
物流効率化法は、現代社会が直面するさまざまな課題に対応するために制定された。ECの普及によって翌日配送などのサービスが一般化し、物流業界は大きな変化を迎えている。人手不足や過重労働の問題も深刻化している。環境負荷の増大やCO2削減への対応も求められている。2024年問題として、トラックドライバーの労働時間規制が企業の売上や利益に影響を与える可能性がある。
課題 | 説明 |
|---|---|
ECの普及 | ECが急速に普及し、翌日配送などのサービスが物流業界に影響を与えている。 |
人手不足と過重労働 | 労働力不足が深刻化し、過重労働の問題が顕在化している。 |
環境問題への対応 | CO2削減など、環境負荷の増大に対処する必要がある。 |
2024年問題 | トラックドライバーの労働時間規制により、企業の売上や利益に影響が出る可能性がある。 |
物流効率化法の目的は、これらの課題を解決し、業界全体の効率化と安全性向上を目指すことである。国や業界団体は、デジタルトランスフォーメーションの活用やICT技術、AI、IoTによる業務の自動化・最適化を推進している。
課題解決(人手不足、物流コストの高騰、環境負荷の増大への対応)
効率化(デジタル技術による業界全体の効率化)
安全性向上(ICTやAI、IoTの活用による業務の自動化・最適化)
荷主に求められる役割
物流効率化法の施行により、荷主には新たな責任が求められている。彼らは物流効率化への積極的な取り組みを行う必要がある。効率化努力義務の遵守や運送契約の書面化も重要なポイントとなる。物流状況の定期的な評価と改善計画の策定が求められる。データ管理体制の構築や安全管理、コスト管理、品質向上も荷主の役割に含まれる。
物流効率化への積極的な取り組み
効率化努力義務の遵守
運送契約の書面化
物流状況の定期的な評価と改善計画の策定
データ管理体制の構築
安全管理
コスト管理
品質向上
荷主がこれらの役割を果たすことで、物流業界全体の持続可能な発展につながる。物流効率化法は、企業の競争力強化にも寄与する重要な法律である。
新規定のポイントと荷主への影響
主な規定と義務
2024年5月の法改正により、物流効率化法は荷主にも新たな義務を課している。荷主と物流事業者は、物流効率化のための努力義務を負う。一定規模以上の事業者は「特定事業者」として、中長期計画の作成や定期報告が必要となる。荷主は物流統括管理者(CLO)の選任も義務付けられている。さらに、荷待ち時間の短縮や物流データの標準化、物流サービスに応じた価格の把握も求められる。
罰則/行政指導 | 内容 |
|---|---|
勧告 | 物流効率化の取り組みが不十分な場合、事業所管省庁から勧告される。 |
命令 | 勧告に従わなかった場合、取り組みをするよう命令される。 |
罰金 | 命令に違反した場合、100万円以下の罰金が科せられる。 |
報告徴収 | 特定事業者に対して報告を徴収することがある。 |
立入検査 | 物流拠点に立入検査を行う場合がある。 |
罰金(報告違反) | 規定による報告をしなかった場合、50万円以下の罰金が科せられる。 |
2025年4月からは業務効率化への取り組みが求められ、コスト削減が期待される。2026年4月以降は法的責任が生じ、物流業務の効率化が一層重要となる。輸送網の集約やモーダルシフトも進み、流通業務の効率化が図られる。
努力義務と判断基準
物流効率化法の改正により、全ての荷主と物流事業者に努力義務が課された。努力義務の内容には、ドライバーの荷待ち時間削減や積載効率の向上が含まれる。荷主は寄託先の倉庫と協力し、効率的な受渡しを実現することが求められる。物流データの標準化やトラック予約受付システムの導入も推奨されている。
荷主の種類 | 努力義務の内容 |
|---|---|
第一種荷主 | 貨物の運送を委託する際、積載効率の向上や荷待ち時間の短縮に努めること。 |
第二種荷主 | 貨物の受渡しにおいて、第一種荷主との協力を行い、効率的な受渡しを実現すること。 |
努力義務は法的拘束力を持たないが、怠ると行政指導や損害賠償請求のリスクがある。行政や業界団体はガイドラインを公表し、適切なリードタイムの確保や物流データの標準化を推奨している。今後は義務規定に改正される可能性もあるため、荷主は積極的な対応が求められる。
物流効率化法対応の手順

現状把握と対象確認
企業が物流効率化法に対応するためには、まず自社の現状を正確に把握することが重要である。現状把握の際には、経営状況や物流業務の可視化が役立つ。たとえば、クラウド型システムを活用すれば、リアルタイムでの位置情報取得や業務の「見える化」が可能となる。
また、清掃・点検チェックリストの作成や、委託先が作業エリアの基準を守っているかの確認も欠かせない。
クラウド型システムによる位置情報のリアルタイム取得
経営状況のデジタル「見える化」
清掃・点検チェックリストの活用
委託先の作業基準の確認
物流効率化法の対象となる荷主かどうかを判断するには、年間取扱貨物量や契約形態を確認する必要がある。下記の表は、対象となる荷主の種類と判定基準を示している。
荷主の種類 | 説明 |
|---|---|
特定第一種荷主 | 自ら運送会社と契約を締結し、貨物の発送を行う企業(発荷主) |
特定第二種荷主 | 物流手配は行わず、貨物を受け取る立場の企業(着荷主) |
判定基準 | 年間取扱貨物量が9万トンを超えることが必要。実際に運んだ貨物の重量が評価対象。 |
社内体制の整備
物流効率化法に対応するには、社内体制の整備が不可欠である。推奨される組織体制や担当部署の例を以下の表にまとめた。
推奨される組織体制 | 説明 |
|---|---|
物流統括管理者の選任 | 物流の責任者を設置し、経営幹部クラスが推奨される。 |
物流部門の新設 | 物流を担当する専任の部門を設ける。 |
各部署の責任者の巻き込み | 調達部、生産部、購買部、販売部などの責任者を巻き込む。 |
物流に特化した人材の育成 | 専門的な知識を持つ人材を育成する。 |
外部からの人材採用 | 物流に詳しい外部人材を採用する。 |
コンサルティングの活用 | 外部の物流コンサルタントを活用する。 |
他社の成功事例では、スモールスタートで実証実験を行い、効果を可視化する方法が有効である。ユーザーの現場課題から逆算して設計することや、信頼できる外部パートナーとの協業も成果につながっている。未来のニーズを見越した体制づくりも重要である。
小規模な実証実験で効果を確認
現場の課題を基にした設計
外部パートナーとの協業
未来のニーズを見据えた体制構築
物流事業者との連携
物流効率化法の実践には、物流事業者との連携強化が欠かせない。荷待ち・荷役時間の削減やドライバーの拘束時間短縮のために、荷役分離やパレット・外装サイズの統一化が有効である。スワップボディコンテナの活用もドライバーの負担軽減につながる。
荷待ち・荷役時間の削減
荷役分離の推進
パレット・外装サイズの統一化
スワップボディコンテナの活用
2025年4月1日施行の新物流2法では、荷主と運送事業者の義務や努力義務が明確化された。デジタコを共通言語とした情報共有や、パネルディスカッションによる実践事例の共有も進んでいる。
実際の事例として、大王製紙株式会社は輸送方法をトラックから船便に変更し、車両台数とCO2排出量を大幅に削減した。福岡運輸株式会社はバース予約・受付システムを導入し、効率的な運用を実現した。アサヒとキリンは共同モーダルシフトでドライバー運転時間を年間2万時間削減した。
物流事業者との連携は、効率化だけでなく環境負荷の低減やコスト削減にも直結する。
Cloudpick JapanのAI無人店舗活用
デジタル技術の活用は、物流効率化法対応の実務において大きなメリットをもたらす。Cloudpick Japanが提供するAI無人店舗やAI物品管理は、荷待ち・荷役時間の短縮や積載効率の向上に役立つ。
AI無人店舗では、AIカメラや重量センサーが商品の動きを自動で記録する。これにより、物品の入出庫や在庫管理がリアルタイムで「見える化」される。人手による確認作業が不要となり、荷役時間の短縮が実現する。さらに、RFIDを使わずに効率的な物品管理が可能となるため、コスト削減にもつながる。
AI無人店舗は24時間365日稼働し、物流拠点や工場、オフィスエリアでの物資管理にも応用できる。これにより、荷主は物流事業者との連携を強化し、積載効率の最大化やドライバーの待機時間削減を実現できる。
AIカメラと重量センサーによる自動記録
在庫管理のリアルタイム化
荷役・荷待ち時間の短縮
積載効率の向上
Cloudpick Japanのソリューションは、デジタル技術を活用した物流効率化法対応の実例として注目されている。多くの企業が導入し、業務効率や現場の生産性向上を実感している。
デジタル化の推進は、今後の物流現場における競争力強化の鍵となる。
実務上の注意点と課題
よくある誤解と対策
現場では、物流効率化法への対応に関して多くの誤解が生じやすい。特に法令遵守や取引慣行、運送会社との連携に関する理解不足が目立つ。下記の表は、代表的な誤解とその対策をまとめている。
誤解の内容 | 有効な対策 |
|---|---|
定期的な法令研修の実施 | |
適正な取引慣行の理解不足 | 荷待ち時間の削減 |
運送会社との密接な連携 |
企業はこれらの誤解を放置せず、社内教育や現場での実践を通じて正しい知識を浸透させる必要がある。
物流事業者との協議ポイント
荷主と物流事業者が協議を行う際には、押さえておくべきポイントがいくつか存在する。主な議題は以下の通りである。
コストの適正化
契約慣行の見直し
運賃と付帯作業の明確な区分
発着予約システムの導入
荷待ち時間や積載率の可視化
法令や制度の理解
顧客ニーズの多様化やEC市場の成長、小口配送の増加など、物流現場は日々変化している。伊藤ハム物流株式会社では共同配送を導入し、最大40%の輸送コスト削減や月間配送費の大幅な改善を実現した。こうした成功事例からも、協議の質が物流効率やコストに直結することが分かる。
継続的な改善のコツ
物流効率化法対応を持続的に進めるには、PDCAサイクルの活用が有効である。現状分析から始め、改善目標を設定し、具体的な施策を実行する。効果を定量的に評価し、次のサイクルに活かすことで、現場の課題を着実に解決できる。
ステップ | 内容 |
|---|---|
計画 (Plan) | 現状分析と改善目標の設定 |
実行 (Do) | 具体的な改善策を実施 |
評価 (Check) | 定量的なKPI設定により効果を測定 |
改善 (Action) | 次のサイクルに向けた調整を行う |
また、データ分析や在庫管理の自動化、レイアウト最適化なども有効な手法である。特定荷主制度や中長期計画、定期報告の仕組みを活用することで、経営層が物流効率化に積極的に関与できる。補助金や税制優遇などの支援策も積極的に活用したい。
継続的な改善を実践することで、企業は法令遵守だけでなく、競争力の強化やコスト削減も実現できる。
荷主は物流効率化法への対応を継続するため、現場負担を抑えつつ営業貢献につながる工夫を意識している。例えば、対応メモのテンプレ化やチャットでのタグ付けは短時間で実践できる。
提案内容 | 工数 | 現場負担 | 営業貢献 |
|---|---|---|---|
対応メモのテンプレ化 | 5分 | ★☆☆☆ | ★★★☆ |
メール一言アピール追加 | 2分 | ★☆☆☆ | ★★☆☆ |
チャットにタグ付け | 0分 | ★☆☆☆ | ★★★☆ |
社内外の連携強化には、EDI連携やペーパーレス化、トラック予約受付システムの導入が効果的である。まずは一部の取引先から段階的に始めることで、スムーズな業務改善が可能となる。社会動向や法改正にも柔軟に対応し、現場の声を経営層が吸い上げる姿勢が重要である。荷主は小さな一歩から始め、持続的な改善を目指している。
